相続税 相続税について
基礎控除額
相続税は相続財産の額が一定額(基礎控除額)を超えることにより発生し、税務署への申告が必要になります。
税制改正により、平成27年1月1日以降に相続が開始されるものから基礎控除額が減額されることになりました。
基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
なお、平成26年12月31日以前に相続が開始していた場合は、
基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
(例)平成27年1月1日以降に相続が開始し、相続人が配偶者と子供2人の場合
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円(基礎控除額)
2.主な税額控除、非課税財産等
相続税の納税については、各相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって受けた利益を限度として、お互いに連帯して納付する義務があります。
主な税額控除、非課税財産等には次のようなものがあります。
(1)暦年課税に係る贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(居住用不動産及び金銭で、贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分を除く)がある場合には、その財産の価額は、相続財産の価額に合算されて相続税が計算され、その代わり、贈与を受けた際に支払った贈与税額が控除されます。
(2)配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が遺産を相続した場合、その金額が法定相続分に達するまでは相続税がかからず、法定相続分を超える場合でも、その金額が1億6千万円以下のときは相続税がかかりません。
具体的には、次より計算した税額が軽減されます。
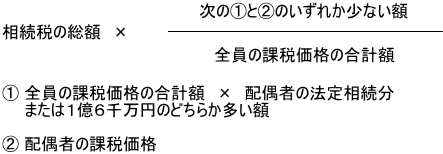
(3)小規模宅地等の評価減の特例
被相続人又は被相続人と同一生計の親族(以下「被相続人等」という)が事業又は居住の為に使用していた土地又は一定の建物(以下「宅地等」という)の評価額を一定の要件で減額することができます。
但し、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与で取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等については、この特例は受けられません。
| 区分 | 要件 | 限度面積 [㎡] |
減額率 [%] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被相続人等の居住の為に使用されていた宅地等 | ア | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330 | 80 | ||
| 被相続人等の事業の為に使用されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | イ | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 特 定 事 業 用 宅 地 等 |
400 | 80 |
| 貸付事業用の宅地等 | ウ | 特定同族会社事業用宅地等(一定の法人の事業の為に使用されていたものに限る) | 400 | 80 | ||
| エ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50 | |||
(注)次の1又は2のいずれかに該当するかに応じて、限度面積を判定します。
1 特定居住用宅地等(ア)及び特定事業用宅地等(イ又はウ)
ア≦330㎡ また、イ+ウ≦400㎡ 合計730㎡
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用可能!
2 貸付事業用宅地等(エ)及びそれ以外の宅地等(ア、イ又はウ)
ア×200/330+(イ+ウ)×200/400+エ≦200㎡
(例)被相続人が亡くなった時に居住していた家屋の敷地
300㎡、評価額2,000万円
2,000万円×(1-0.8)=400万円
減額率80%、1,600万円減額!
<特定事業用宅地等>
被相続人等の事業(貸付事業を除く)の為に使用されていた宅地等で次の表に該当するもの。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 被相続人の事業の為に使用されていた宅地等 | その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること |
| その宅地等を相続税の申告期限まで有していること | |
| 被相続人と同一生計の親族の事業の為に使用されていた宅地等 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること |
| その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
<特定居住用宅地等>
被相続人等の居住の為に使用されていた宅地等で次の表に該当するもの。
複数ある場合は主にその居住の為に使用されていた宅地等に限ります。
被相続人と親族が二世帯住宅に居住していた場合や被相続人が老人ホームなどに入居又は入所していた場合でも、一定の要件を満たせば、特例の適用を受けることができます。
| 区分 | 要件 | |
|---|---|---|
| 取得者 | 取得者ごとの要件 | |
| 被相続人の居住の為に使用されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | 要件なし |
| 被相続人と同居していた親族 | 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 | |
| 被相続人と同居していない親族 | アからウの全てに該当する場合で、かつ、次のエ及びオの要件を満たす人 ア 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有してない場合で日本国籍を有していること イ 被相続人に配偶者がいないこと ウ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の為に使用されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと エ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の為に使用されていた家屋を除く)に居住したことがないこと オ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
|
| 被相続人と同一生計の親族の居住の為に使用されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | 要件なし |
| 被相続人と同一生計の親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 | |
<特定同族会社事業用宅地等>
一定の法人の事業(貸付事業を除く)の為に使用されていた宅地等で次の表に該当するもの。
一定の法人とは、相続開始直前に被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額が50%を超えているその法人(清算中の法人を除く)のこと。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 一定の法人の事業の為に使用されていた宅地等 | 相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除く))であること |
| その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
<貸付事業用宅地等>
被相続人等の貸付事業の為に使用されていた宅地等で次の表に該当するもの。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 被相続人の貸付事業の為に使用されていた宅地等 | その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること |
| その宅地等を相続税の申告期限まで有していること | |
| 被相続人と同一生計の親族の貸付事業の為に使用されていた宅地等 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること |
| その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
(4)死亡保険金・死亡退職金の非課税
全ての相続人(相続を放棄した者や相続権を失った者を除く)の取得した死亡保険金の合計額又は死亡退職金の合計額が下記の非課税限度額以下である場合(死亡保険金と死亡退職金は別々に計算)、各相続人の取得した死亡保険金又は死亡退職金の全額が非課税となります。
| 死亡保険金の非課税 | 死亡保険金の非課税 | |
|---|---|---|
| 平成23年3月31日 以前の相続等 |
500万円×法定相続人の数(注1) | 500万円×法定相続人の数(注1) |
| 平成23年4月1日 以後の相続等 |
500万円×法定相続人の数(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)(注1) | |
なお、これらの税額軽減を受けるためには、相続税の申告期限内に遺産の分割が行われていることが必要です。また、遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(相続人全員の印鑑証明書を添付したもの)などを相続税申告書に添付する必要があります。
ただし、相続税の申告期限内に遺産の分割が行われなかった場合でも、申告期限後3年以内に分割される等、一定の場合にはこの税額軽減を受けることができます。
相続税には、この他にも農業を継続していく場合に受けられる相続税の納税猶予の特例等、様々な税務上の特例があります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧頂くか、税理士にご相談下さい。
3.準確定申告について
年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
故人に代わって申告・納税する人は、相続人または包括受遺者です。
準確定申告が必要となるのは、故人が以下の要件に該当する場合です。
1.2カ所以上から給与を受けていた場合。
2.給与収入が2,000万円を超えていた場合。
3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。
4.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合。
5.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合。
※上記の要件にあてはまらない人の場合は、準確定申告をする必要はありません。
※申告書の提出先は、故人の住所地を管轄する税務署です。
4.申告と納税について
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(亡くなった日等)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ行います。
また、納税は、金銭で一時に納めるのが原則ですが、一定の要件を備えた場合に限って、延納と物納が認められています。
※相続税の納税については、各相続人が相続、遺贈が相続時精算課税に係る贈与によって受けた利益の限度として、お互いに連帯して納付する義務があります。
(1)延納
相続税を納付期限までに金銭で納付することが困難な場合には、その困難とする金額を限度として、法律で定められた年数(相続財産に占める不動産等の価格の割合に応じ、最高20年)で、年賦により分割納付をすることができます。
この延納を利用するためには、納期限までに、延納申告書及び担保期限関係書類を提出する必要があります。
(2)物納
相続税を納期限までに、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、その納めることができない金額を限度として、一定の相続財産により納付をすることができます。
この物納を利用するためには、納期限までに物納申請書及び物納手続関係書類を提出する必要があります。
バナースペース
河村慈高司法書士事務所
〒617-0004
京都府向日市鶏冠井町大極殿65-22
TEL : 075-934-0600
FAX : 075-922-6164
E-Mail :
kawamura-touki@mbr.nifty.com
※ご相談は、まずはお電話でお願い
いたします。
阪急京都線西向日駅北口から徒歩5分。
旧京都地方法務局向日出張所南隣です。
当事務所はオンライン申請により、日本
全国の登記申請に対応しております。
遠方の方も、お気軽にご相談ください。
女性司法書士が在籍しております。
ご希望の方は、お申し付けください。
